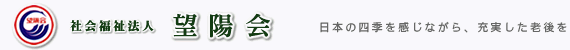| (入所者の資格) |
| 第6条 |
| 1.ケアハウスは、次の各号のすべてに該当する方に限り利用することができる。 |
 |
- 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことついて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な方。
- 年齢が60歳以上である方。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者についてはこの限りでない。
- 家族と同居することが困難な方。
- 伝染病疾患がなく、かつ問題行動を伴わない方で共同生活が可能な方。
- 生活費をまかなうことができる所得等があり、所定の利用料を継続的に支払うことが可能な方。
- 身元保証人が得られる方。ただし、真にやむを得ない特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
|
 |
| 2.前項第6号ただし書きに該当する方は、次の各号に関するケアハウス所定の覚書を提出するものとする。 |
 |
- 利用料等の支払に必要な事項
- 医療機関の受診に関する事項
- その他必要事項
|
 |
| (利用料の受領) |
| 第7条 |
| 1.ケアハウスは、次の各号のすべてに該当する方に限り利用することができる。 |
 |
- サービスの提供に要する費用(入所者の所得状況その他事情を勘案して徴収すべき費用として柏市長が定める額。)
- 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して柏市長が定める額
- 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)
- 居室に係る光熱水費
- 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
- 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
|
 |
| 2.入所者は、毎月の利用料をケアハウスの指定する日までに指定の方法により支払わなければならない。 |
 |
| 3.入所者は、利用料等の支払い、損害の賠償、原状回復費用その他この契約から生じる債務を担保するため、入居契約締結と同時に入居時預り保証金を支払うものとする。 |
 |
| 4.サービスの提供に要する費用の減額を希望する入所者は、入所者の前年分(収入申告をする日が1月から6月までの間の日である場合にあっては、前々年分)の収入等に関する挙証資料を添付し、施設長に対して申請を行わなければならない。 |
 |
| (サービスの提供方針) |
| 第8条 |
| 1.入所者が、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 |
 |
| 2.職員は、入所者に対するサービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 |
 |
| 3.入所者に対するサービスの提供にあたっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 |
 |
| 4.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 |
 |
| (相談、援助) |
| 第9条 |
| 入所者に対しては、各種相談に応ずるとともに余暇の活用及び在宅福祉サービスの活用など必要な助言その他の援助を行うものとする。 |
 |
| (居宅サービス等の利用) |
| 第10条 |
| 入所者が要介護状態等となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(ホームヘルプサービス、デイサービス等)を受けることができるよう、必要な援助を行う。また、居宅介護支援事業の居宅サービス計画書に基づき利用することができる。 |
 |
| (居 室) |
| 第11条 |
| ケアハウスが提供する居室は原則個室とする。その際、選択する階及び居室は、入所者の希望ではなく、施設側で入所者の心身の状態を鑑み選定することとする。 |
 |
| (食事サービス) |
| 第12条 |
| 1.食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮したものとする。 |
 |
| 2.食事の時間は、次の通りとする。 |
 |
- 朝食 08時00分〜
- 昼食 12時00分〜
- 夕食 18時00分〜
|
 |
| 3.あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間(2時間以内)、食事の取り置きをすることができる。 |
 |
| 4.最低1日前に、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。 |
 |
| 5.食材費の返還は入所者の入院4日目から退院までの日数に対して行い、その他の場合には、理由の如何を問わず、返還しない。ただし、行事特別食の差額部分については、当該行事の1週間以上前にケアハウス所定の用紙で届け出た場合のみ、請求をしない。 |
 |
| (入浴) |
| 第13条 |
| 1.入所者の入浴については、施設内に設けた入浴設備を利用して、原則として毎日入浴の機会を提供し、入所者の清潔の保持に努めるものとする。ただし、毎月、第一、第三月曜日は、浴槽の乾燥のため、入浴を休みとする。 |
 |
| 2.入所者に対する個別の入浴介助は、原則として行わないものである。ただし、介助を必要とする状態となった場合は、ケアハウスは介護保険をはじめ各種の居宅サービスによる入浴介助を受けることができるよう迅速な対応に努める。 |
 |
| 3.前項の入浴介助に必要な費用は、入所者の負担とする。 |
 |
| 4.入浴時間は原則として午後4:00〜7:30とする。 |
 |
| (緊急時の対応) |
| 第14条 |
| 1.身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。 |
 |
| 2.職員はナースコール等で入所者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対応を行うものとする。 |
 |
| 3.入所者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。 |
 |
| (健康の保持) |
| 第15条 |
| 1入所者について、健康の保持をするため定期的に健康診断を行うなど必要な指導援助を行うものとする。 |
 |
| 2.入所者から健康に係る相談を受けたときは、速やかに医療機関等の紹介など必要な援助を行うものとする。 |
 |
| (社会生活上の便宜の供与) |
| 第16条 |
| 1入所者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者が行うことが困難である場合は、申し出及び同意に基づき、施設が代わって行うことができる。 |
 |
| 2.入所者の希望により、要介護認定の更新や再認定の代行業務を行う。 |
 |
| (協力医療機関等) |
| 第17条 |
| 1入所者の心身の状態の異変その他緊急事態に備えるため、下記の協力医療機関を定める。緊急時には主治医又は同協力医療機関にて適切な措置を講ずる。 |
 |
| 医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
| 柏の葉北総病院 |
流山市駒木台233-4 |
04-7155-5551 |
| 千葉・柏たなか病院 |
柏市若柴110 |
04-7131-4131 |
|
 |
| 2.入所者に健康上の急変があった場合は、関係機関もしくは適切に医療機関と連絡を取り救急医療等の適切な措置を講ずる。 |
 |
| (利用の申込み) |
| 第27条 |
| 1.ケアハウスへの利用希望者は、利用申込書(別紙様式1)を提出するものとする。 |
 |
| 2.ケアハウスは、利用申込書の提出があったときは、その内容を確認のうえ、利用申込者名簿に登録しなければならない。 |
 |
| (利用希望者の面接調査) |
| 第28条 |
| 1.利用希望者の調査は、入所者本人及び保証人との直接面接により行うものとする。 |
 |
| 2.前項の調査に当たっては、入所者本人の健康診断書(別紙様式2)の提出を求め健康状態を確認するものとする。 |
 |
| (利用の承認等) |
| 第29条 |
| 前条の調査の結果、利用を適当と認めた方に対しては、利用を承認する旨を、また利用を不適当と認めた方に対しては、利用を不適当と認めた旨をいずれも文書をもって本人宛通知しなければならない。 |
 |
| (入居契約の締結) |
| 第30条 |
| 利用にあたっては、あらかじめ、利用申込者及びその家族に対し、入居契約書及びその別様式、重要事項説明書及びその別紙を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で入居契約書を締結するものとする。 |
 |
| (入所者台帳の整備) |
| 第31条 |
| 新たな入所者については、入居時の健康診断を行うとともに、入所者の従来の生活状況、家族状況等必要な事項の聴取を行い、それらの調査結果を入所者台帳に記録整備する。 |
 |
| (居室の変更) |
| 第32条 |
| 入所者が次の各号の一に該当するときは居室を変更することができる。 |
 |
- 入所者の身体機能の低下等のため、居室を変更することが適当と認められたとき。
- 前各号のほか、居室の変更が必要と認められるとき。
|
 |
| (退所) |
| 第33条 |
| 入所者が次の各号の一に該当する場合には入居契約を終了とする。 |
 |
- 入所者の死亡。
- 入所者から退所届(別紙様式3)の提出がありこれを受理したとき。
- 次条の規定により入居契約を解除したとき。
|
 |
| (入居契約の解除) |
| 第34条 |
| 1.施設長は、入所者が次の各号の一に該当すると認めたときは入居契約を解除することができる。 |
 |
- 不正またはいつわりの手段によって利用承認をうけたとき。
- 正当な理由なく利用料を滞納したとき、又は支払うことができなくなったとき。
- 居宅介護サービス提供を利用してもなお介護を必要とし、ケアハウスでの生活が著しく困難となったとき等ケアハウス(介護型)や特別養護老人ホーム入所対象程度の心身の状況になったとき。
- 身体又は精神的疾患等のため、施設での生活が著しく困難となったとき。
- 入院し、医師の診断により3ヶ月以内に退院できる見込みがないか又は入院後3ヶ月経過した場合であって、退院後も上記(3)または(4)の状況であろうと施設長が判断したとき。
- 承認を得ないで、施設の建物、付帯設備等の造作・模様替えを行い、かつ、原状回復をしないとき。
- 金銭の管理、各種サービスの利用について入所者自身で判断ができなくなったとき。
- 前各号のほか、共同生活の秩序を著しく乱し他の入所者に迷惑をかけるなど、ケアハウスの生活が著しく不適当と思われる事由が生じたとき。
|
 |
| 2.施設長は、入居時に契約の解除となる条件について、十分説明し、契約を解除するに至った場合、具体的に理由を明示するものとする。理由が上記(3)、(4)、(5)である場合は、入居者本人及び家族の希望を勘案し、本人の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう、他の福祉・医療サービス事業者とも連携し、必要な援助に努める。 |
 |
| (転貸等の禁止) |
| 第35条 |
| 入所者は、居室を転貸、又は譲渡もしくは入所者以外の方を同居させることができない。 |
 |
| (苦情への対応) |
| 第37条 |
| 1.ケアハウスは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じるものとする。 |
 |
| 2.苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容を記録するものとする。 |
 |
| 3.その提供したサービスに関し、柏市から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。 |
 |
| 4.柏市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を柏市に報告する。 |
 |
| 5.社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力する。 |
 |
| 6.苦情申立窓口は、重要事項説明書および別掲ケアハウス苦情・相談解決制度に記載されたとおりである。 |
 |
| (施設・設備) |
| 第38条 |
| 1.施設・設備の利用時間や生活ルール等は、施設長が入所者の意見も勘案の上決定するものとする。 |
 |
| 2.施設・設備等の維持管理は職員が行うものとする。 |
 |
| (葬儀) |
| 第39条 |
| 死亡した入所者に葬儀を行う方がいない時は、施設長は、老人福祉法第11条2項の規定等により関係区市町村と協議して葬儀を行うものとする。 |
 |
| (身体拘束の手続き) |
| 第40条 |
| 入所者本人の行動等によって、入所者本人、他の入所者、家族、または職員等、施設内にいる者の生命・身体に切迫した危険があり、それを防ぐ代替手段が他にない場合に限り、本人に対し、拘束衣の着衣、車イス上での固定、ベッド上での固定、手足の可動域の制限等の身体拘束を最小限の選択により行う。危険が去ったときは、速やかに拘束を解く。入所者の家族に対しては、極力事前に通知するが、連絡が取れない場合等には、事後速やかに報告する。 |
 |